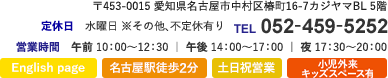2025/03/03
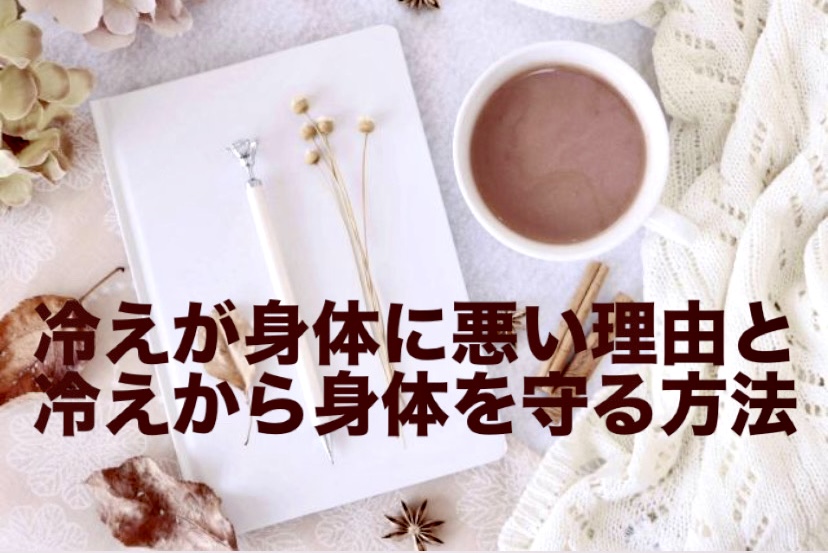
こんにちは!
まだまだ寒い日が続きますね。
「冷えは万病の元」とことわざにもあるくらい、体を冷やすことは良くないことと言われています。
それでは、何故冷えが身体に良くないと言われているのでしょうか?
今回は、冷えが身体に悪い理由と身体を冷えから守る方法をまとめてご紹介していきます!
〇冷えが身体に悪い理由
冷えが身体に悪い理由はズバリ、冷えが私たちにとって様々な健康問題を引き起こす原因となり得るからです。
私たちの身体は、温かさを保つことによって健康を維持しています。
実際に、冷えが身体に悪い理由を7点挙げ、それぞれについて詳しく解説していきます!
1. 血行不良
血液は体内の酸素や栄養素を運ぶ重要な役割を果たしています。冷えによって血管が収縮し、血行が悪化するため、全身に必要な栄養や酸素が行き渡りにくなります。これにより、身体は疲労を感じやすくなり、ドロップ感や倦怠感を引き起こすことがあります。また、慢性的な血行不良は、しびれやむくみの原因ともなるため、注意が必要です。
2. 免疫力の低下
体温が下がると、免疫機能も低下します。免疫システムは、外部からの病原体や感染症に対抗する重要な役割を担っていますが、冷えにより免疫細胞の活性が低下すると、風邪やインフルエンザなどにかりやすくなります。特に冬場は、冷えが感染症の引き金となることが多いため、注意が必要です。また、長期的に免疫力が低下すると、自己免疫疾患やアレルギーのリスクも高まります。
3. 新陳代謝の低下
冷えは、基礎代謝を妨げる要因でもあります。体温が低下すると、新陳代謝が鈍くなり、脂肪の燃焼が効率よく行われなくなります。その結果、体重が増加しやすくなります。特にダイエットを意識している人にとっては、冷えは大敵です。また、新陳代謝の低下は、肌や髪の健康にも悪影響を及ぼします。血行不良と相まって、肌のくすみや髪の乾燥が進行することがあります。
4. 内臓機能の低下
冷えは内臓に対しても深刻な影響を及ぼします。特に腸は温度に非常に敏感で、冷えると消化不良や便秘を引き起こしやすくなります。腸内環境が悪化すると、栄養の吸収が妨げられ、健康全般に悪影響を与えます。さらに、腸が冷えることで腸内のバランスも崩れ、健康な腸内細菌が減少することも問題です。これらの影響は、免疫力や精神的な健康にも波及します。
5. 精神的な影響
冷えは身体だけでなく、心にも影響を及ぼします。体温が下がると、リラックスしにくなり、ストレスや不安感が増すことがあります。冷えによる不快感がストレスを増加させ、その結果、身体全体のコンディションをさらに悪化させます。また、睡眠の質にも影響を与え、心身の回復が妨げられます。良好な精神状態を維持するためには、心地よい体温を保つことが重要です。
6. 関節や筋肉の痛み
寒さは筋肉を緊張させ、血行を悪化させるため、関節や筋肉に不快な痛みを引き起こすことがあります。特に冷え性やリウマチに悩む人にとって、冷えは痛みを悪化させる大きな要因です。冷えることで筋肉が硬くなり、運動の際に負担をかけやすくなります。このような悪循環が続くと、慢性的な痛みや運動不足に繋がることがあるため、早期対策が求められます。
7. 睡眠の質の低下
冷えは睡眠にも影響を及ぼします。体が冷えていると、寝つきが悪くなり、深い睡眠を得ることが難しくなります。睡眠は心身の健康を保つために欠かせない要素ですが、冷えによる不快感が寝返りを促し、眠りが浅くなることがあります。結果的に、翌日には疲労感が残り、集中力やパフォーマンスに悪影響を及ぼします。質の良い睡眠を得るためには、体を冷やさない工夫が必要です。
冷えは身体にさまざまなマイナスの影響を及ぼす要因であり、特に現代社会においては多くの人々がこの問題に直面しています。血行不良や免疫力の低下、新陳代謝の悪化など、冷えが引き起こす影響は多岐にわたり、放置すると深刻な健康問題に繋がる可能性があります。日常生活において冷えを防ぐための工夫を行い、健康を維持することが重要です。冷えの対策を講じることで、心身ともに健やかな生活を送ることができるでしょう。
それでは次に、冷えから身体を守る方法について挙げていきます!

〇身体を冷やさないための対策
体を冷やさないために、日常生活の中で具体的に何をしたらいいのでしょうか?
ここでは、冷え対策として効果的な7つの方法を詳しく紹介していきます!
1. 暖かい服装を選ぶ
寒い季節には、適切な服装が非常に重要です。重ね着をすることで体温を逃がさず温かく保つことができます。特に、首、手首、足首などの「三首」を冷やさないように注意しましょう。これらの部分は体温が逃げやすく、冷えると全身に影響が及びます。ウールやフリースなどの暖かい素材を選ぶことがポイントです。
2. 意識的な温活を実践する
日常生活に温活を取り入れることで冷えを防ぐことができます。例えば、温かい飲み物(生姜茶やハーブティー)を摂取することで、体を内側から温めることができます。また、入浴は血行を促進し、温まるだけでなく、リラックス効果も期待できるため、毎日の習慣にすることをおすすめします。40度前後のお湯にゆっくり浸かることで、筋肉の緊張もほぐれ心身ともにリフレッシュできます。
3. 適度な運動を心がける
運動は血行を促進し、基礎代謝を上げるために非常に効果的です。特に、ストレッチやウォーキングなどの軽い運動は、体を温かく保つだけでなく、筋肉を柔らかくし、冷えの改善に役立ちます。仕事の合間に軽く体を動かす習慣を取り入れることが大切です。また、体を動かすことで精神的にもリフレッシュでき、ストレスの軽減にもつながります。
4. 食生活を見直す
食事は体温に大きな影響を与えます。特に、体を温める食材を積極的に取り入れることが重要です。生姜、唐辛子、にんにくなどの香辛料を使った料理や、温かいスープや煮物を食べることで、内側から体を温めることができます。さらに、ビタミンやミネラルを豊富に含む食品、特に緑黄色野菜を摂取することも大切です。栄養バランスの取れた食事を心がけ、体を冷やさない食材を選びましょう。
5. 定期的にカイロプラクティックの施術を受ける
身体の冷えを和らげるために、定期的にカイロプラクティックの施術を受けることも有効です。
カイロプラクティックは身体の構造(特に脊椎)と機能に注目した専門医療です。
カイロプラクティックの施術法は、施術者によって様々ですが、主に脊椎やその他の身体部位を手技によって調整(矯正)することにより、身体機能が改善され、自己治癒力を高めることを目的としています。背骨や関節の調整を行うことで、自律神経のバランスが整えられ、体温管理がスムーズになります。定期的な施術を受けることで、冷え性改善や体調の向上に繋がるでしょう。
6. 睡眠環境を整える
良好な睡眠を得るためには、寝室の環境を整えることが欠かせません。温かい布団や寝具を使い、快適な温度を保つことで睡眠の質を向上させることができます。また、寝る前にホットミルクやハーブティーを飲むことで、体を内部から温めることができます。さらに、冷え性の人は足元を冷やさないように、靴下を履いて寝るのも良い方法です。寝室の温度管理も大切ですので、季節や気温に応じた調整を心がけましょう。
7. リラックスする時間を持つ
ストレスが溜まると、体が緊張した状態になり、血行が悪くなり、冷えにつながります。心身の健康を維持するためには、リラックスする時間を持つことが大切です。ヨガや瞑想、深呼吸などのリラクゼーション法を取り入れることで、心を落ち着け、体の緊張を解消することができます。リラックスがもたらす効果は、体温を安定させる上でも重要です。自分に合ったリラックス法を見つけて、日常生活に取り入れましょう。
さて、今回は「冷えが身体によくないのは何故なのか」ということにスポットを当ててまいりました。 冷えによって健康が損なわれる前に、ぜひ今回挙げた冷え対策を実践してみてください
最後に、対策の一つとして挙げたカイロプラクティックの重要性についてご紹介します!

〇カイロプラクティックの重要性
冷え対策を実践することは、身体の健康を維持するために非常に重要です。そして、これらの方法と併せて考えたいのがカイロプラクティックです。カイロプラクティックは、背骨や関節の調整を通じて神経の働きを正常に保ち、身体全体のバランスを整える治療法です。これにより、血行が改善され、身体が正常に機能するようになります。
冷え性の根本的な改善を図るためには、姿勢の改善や関節の可動域を広げることが有効です。カイロプラクティックでは、身体全体のバランスを考慮し、冷えの原因となる部位に対してアプローチを行います。さらに、冷えによる筋肉の緊張を解消することで、血液の流れが良くなり、身体が内部から温かさを感じるようになります。
また、カイロプラクティックの施術は、ストレスを軽減し、心をリフレッシュさせる効果もあります。リラックスした状態で過ごすことで、より良い睡眠を得られ、冷え性の改善にもつながります。冷えは全身に影響を与えるだけでなく、生活の質を低下させる要因でもあります。そのため、カイロプラクティックを取り入れた包括的なアプローチが、冷えから身体を守るために非常に効果的です。
当院では、WHO基準となる世界保健機関が定めた厳しいカイロプラクティック専門教育を全て修了し、CCEA(アジア大洋州カイロプラクティック教育審議会)により国際的に認証されている正規のDoctor of Chiropractic(D.C.号)/ドクター・オブ・カイロプラクティックの学位・称号のほか、Diplomate of Chiropractic Science(D.C.Sc.号)/カイロプラクティック科学専門家、Bachelor of Chiropractic Science(B.C.Sc.号)/カイロプラクティック理学士など、“世界初”となる3つのカイロプラクティック専門学位・称号を授与され、国際公認試験となる国際カイロプラクティック試験委員会(IBCE)によるカイロプラクティック統一試験(SPEC臨床能力判定試験)にも合格、またカイロプラクティックの本場、アイオワ州デブンポートにある米国パーマーカイロプラクティック大学や、ウィスコンシン州マウントハーブにある米国ガンステッドクリニックなどでの修学、研修を終え、米国や豪州などのカイロプラクティックが法制化されている国や地域と同様となる世界標準、国際基準のカイロプラクティック・ケアの提供をしています。
また、提携医療機関にてカイロプラクティック・ケアに必要となるカイロプラクティック観点からのフルスパイン(骨盤から頭頸部までの前後像と側面像における全身のレントゲン画像)によるレントゲン画像の撮影と分析、解析を行ない、さらには米宇宙財団/NASA認証検査機器による赤外線サーモグラフィー検査や自律神経系のバランス測定検査などにおける各種神経機能検査を行ないながら、来院者様のお身体の構造的そして機能的な状態をしっかりと把握した上で施術の方針を決定していきます。 推測ではなく、正確かつ的確に患者様のお身体を知った上での施術で、本当の健康へと近づくサポートをしてまいります!
もしご自身のお身体でお悩みのあって、施術を受けることを迷われている方に対しましても、毎月先着3名の方に無料相談会も実施しております。
ぜひご利用くださいませ。