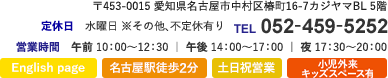2025/04/04
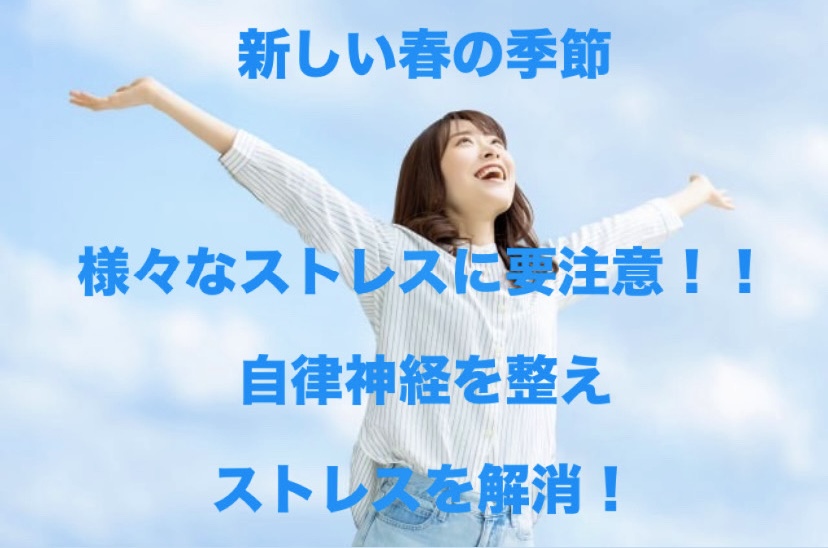
こんにちは!
新年度が始まり、環境の変化に伴って「なんとなく疲れやすい」「肩こりや頭痛がひどい」「よく眠れない」と感じていませんか?
春は新しい生活や仕事がスタートする時期ですが、同時にストレスが増えやすい季節でもあります。環境や気温の変化、生活リズムの乱れ、人間関係のプレッシャーなどが積み重なり、自律神経が乱れやすく頭痛や関節痛、胃腸の不調や食欲不振に繋がる可能性があります。
今回は、春に感じやすいストレスの原因と、それを乗り越えるためのカイロプラクティックの可能性について解説していきます。
1.はじめに、ストレスって何?
ストレスとは、身体に刺激が加えられた時に生ずる反応をストレス、外から加えられる刺激(例:暑さや寒さ)をストレッサーとして概念化されたものです。現在ではストレッサーの意味でもストレスと言うことが多くなってきています。具体的には以下の内容のようなものです。
1.1緊急反応
アメリカの生理学者ウォルター・B・キャノンは動物や人間が緊急事態に遭遇した際に「戦う」または「逃げる」ために身体が自動的に反応することを発見しました。その内容は、
- ① 交感神経の活性化
- 脳が危機を察知すると、自律神経のうち交感神経が活性化する。
- ② ホルモン分泌
- 副腎髄質からアドレナリンやノルアドレナリンが分泌される。
- ③ 身体の変化
- 心拍数と血圧が上昇(酸素供給を増やす目的)
筋肉の緊張(戦うまたは逃げるための準備)
消化機能が低下(エネルギーを温存する)
1.2慢性反応
ストレス学説では、カナダの生理学者・内分泌学者ハンス・セリエは、ストレスは慢性的にも起こりうると提唱し、多くの病人たちが共通して頭痛や関節痛、胃腸の不調や食欲不振を訴える様子に着目しました。そしてストレス反応が3つの段階を経ることを発見しました。その内容は、
- ① 警告反応期
- ストレスを受けると、身体は「戦うか逃げるか」の反応を示し副腎髄質からアドレナリンが分泌され心拍数や血圧が上昇し、筋肉が緊張する。
- ② 抵抗期
- ストレスが続くと、身体は適応しようとして副腎皮質ホルモンが分泌されエネルギー供給が促される。
- ③ 疲弊期
- 長期的なストレスにより、身体の適応機能が限界に達し、免疫力の低下、病気のリスクが高まる。

2.春に感じやすいストレスの原因
2.1季節の影響
春は寒暖差が激しく気温の変化が起こり自律神経に乱れを加えます。
自律神経は、暑い環境では血管を拡張し血流を増やすことで熱を外に逃がしやすくします。
寒い環境では、血管を収縮させ熱を外に逃さないようにします。朝晩と日中の気温差が激しくなると交感神経と副交感神経の切り替えが追いつかず、自律神経のバランスが崩れやすくなりストレスの原因になる可能性があります。
2.2環境の変化
職場の異動や転勤により仕事内容の変化や仕事量の変化、新学期や進学により新しい環境への変化がストレスの原因になる可能性があります。さらに生活リズムの変化、例えば起床時間や通勤時間、通学時間の変化や、外食や飲み会の増加で食生活が乱れることもストレスが加わる原因となります。
2.3人間関係の変化
新しい上司や同僚、クラスメイトとの関係構築、転勤や異動でこれまでの仲間と離れる寂しさ、親しい友人と環境の変化で会えなくなることや、初対面での会話やマナーなどコミュニケーションの不安、「しっかりとしなければいけない」というプレッシャーや緊張がストレスの原因になる可能性があります。
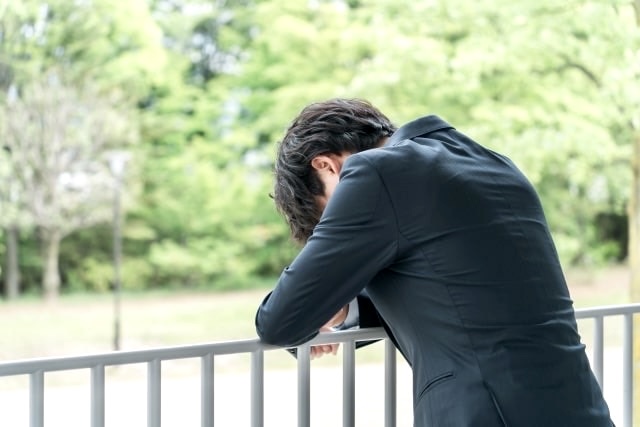
3.ストレスと自律神経の関係
3.1自律神経
自律神経は、胸髄と腰髄から出る交感神経系と、脳幹と仙髄から出る副交感神経系の2つにより構成されています。特徴としては、交感神経は体を活動に適した状態にし、副交感神経は次の活動に備えて体を休息・回復させる役割です。例えば活動時には交感神経活動が高まり、その結果血圧が上昇し心機能が高まり消化管の機能は抑制されます。反対に、副交感神経の活動が高まると、消化管の働きが活発となり食物の消化吸収が促進し、体内でエネルギーや栄養素が蓄えられ、心臓などの働きは抑制されます。
3.2ストレスと交感神経
副腎の内側にある副腎髄質は交感神経によって支配されており、身体にストレスが加えられると交感神経の活動が増加して、ノルアドレナリン、アドレナリン、ドパミンの分泌が増え、身体の様々な器官に作用し血糖値を上げ、心臓の収縮力を増やして交感神経機能全体を高めます。
3.3ストレスが自律神経を乱す仕組み
ストレスを受け続けると、自律神経のバランスが崩れることがあります。短期的なストレスであれば、一時的に交感神経が活性化するだけで自律神経に影響は少ないと考えられていますが、長期間でストレスを受け続けると、交感神経が優位になりすぎて副交感神経の働きが低下し、結果として身体的な不調や免疫力の低下など心身に様々な不調が現れる可能性が高まります。

4.ストレスによる自律神経の乱れを整える方法
4.1リラックスする時間を意図的に作る
ストレスは交感神経を優位にする働きがある為、心身の緊張をほぐす為にもリラックスする時間を作ることが有効となります。例えば自分の趣味に時間を使うのはどうでしょうか。音楽を聴くことについては大脳皮質の広い領域が活動することが解明されており、親しみのある曲ほどリラックス効果が高いといわれています。他にも森林や川沿い、湖畔などの自然の中を散策し、心身の安定を図ることもできます。また、自分にあった「香り」を見つけるのも効果的です。アロマを活用し、ラベンダー、カモミールの香りは自律神経を調整し、リラックス効果を高めます。
4.2生活習慣を整える
生活習慣を整えるためには、心身の健康を維持する為に毎日のリズムを整え、バランスの取れた行動を心がけることが大切です。
- ① 質の良い睡眠をとる
- 毎日同じ時間に寝て起きることで睡眠リズムを一定に保ち、質の良い睡眠を確保します。そして寝る1時間前はブルーライトによる交感神経の刺激を避ける為、スマートフォンやパソコンを見ないようにして副交感神経を優位にさせ、深い呼吸やストレッチをしてから寝るようにしましょう。
- ② 毎日同じ時間に起きる
- 朝起きると交感神経が優位になり、夜になると副交感神経が優位になるのが理想的なリズムです。起きる時間がバラバラだとこのリズムが崩れ、自律神経の乱れに繋がる可能性があります。休日に寝坊をし、体内リズムが崩れ月曜日に疲れが抜けにくくなる経験はないでしょうか。決まった時間に起床し、リズムを整えていきましょう。
- ③ 軽い運動やストレッチ
- 軽い運動やストレッチは、血流を促し、自律神経のバランスを整える効果があります。特に交感神経が過剰に働いている時は、副交感神経を優位にしてくれます。逆に心身に、だるさを感じる時は交感神経を活性化させる作用があります。ウォーキングを20分〜30分程度行うと、副交感神経が優位になるといわれています。リズム良く歩くことを心がけるようにしましょう。
ストレッチは固まった筋肉をほぐし、血流を改善、自律神経を調整するのに適しています。特に首や肩、背中、腰のストレッチが効果的です。仕事や家事の合間にでも簡単にでき、毎日続けることで効果が上がるとされています。 - ④ 入浴
- 入浴は副交感神経を活性化し、心身をリラックスさせるのに最適な方法です。シャワーだけで済ませるよりも、湯船に浸かることで血流が良くなり、自律神経が整いやすくなります。効果的な入浴方法については、副交感神経を活性化させるには体温+3度以内の温度(38度〜40度)のぬるめのお湯に浸かるのがよいといわれています。15分から20分程度じっくりと浸かると血流が良くなり心身がリラックスできます。さらに入浴後にストレッチをすることで筋肉の緊張がほぐれやすく、副交感神経を優位にして快眠にも繋がります。
4.3生活環境を整える
- ①部屋の整理整頓でストレスを軽減する
- 部屋が散らかっていると脳が無意識にストレスを感じます。散らかった部屋は、目に見える「未解決の問題」を常に感じさせるため、脳がリラックスできません。その他、整理整頓ができていない部屋は、無意識に「生活全体が乱れている」という感覚を引き起こすことがあります。これにより、ストレスや不安、焦燥感が増加する可能性があります。
- ②スケジュール管理を工夫する
- スケジュール管理は、ストレスを軽減するための重要な手段です。計画的に時間を使い、タスクを整理することで、無駄なプレッシャーを減らし、心の余裕を生むことができます。
例えば優先順位をつけることが大切です。まずは、「今やるべきこと」を決め、後回しにできることは後に回します。他には、時間をブロックする方法も有効な手段となります。1日の中で特定の時間帯を専用のタスクに充てることで時間ごとの予定が把握しやすく「これから何をすべきか」が明確になり混乱を防ぐことができます。スケジュール管理をする際、完璧にこなそうとすると逆にプレッシャーがかかり、ストレスが増加します。完璧を求めすぎないことが大切です。
4.4カイロプラクティックによる自律神経の調整
ストレスは自律神経にとても影響があると同時に、自律神経は脳と脊髄から全身に広がる神経です。背骨の中には脊髄が通っており、そこから交感神経と副交感神経が分かれ、心身の調整を行なっています。姿勢や背骨の問題があると、神経伝達がスムーズに行われず自律神経の働きが乱れやすくなり不調の原因となります。カイロプラクティックでは、背骨や関節、骨盤の調整をすることで神経の働きを正常に保ち、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。
5.まとめ
新しい春の季節において、季節の変化や環境の変化、仕事や人間関係、社会的なプレッシャー等が重なり合い、かつてないほどのストレスに晒されています。これらのストレスは精神的な疲れだけではなく、身心的な不調や生活の質にも深刻な影響を与える可能性があります。今回は、ストレスと上手に向き合い、管理するいくつかの方法をご紹介しました。自身のセルフケアで生活習慣、生活環境を整え、リラックスできる時間を意図的に作ることが大切です。一方、カイロプラクティックでは、背骨や関節、骨盤の調整をすることで神経の働きを正常に保ち、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。セルフケアと専門的なケアを組み合わせ、より効果的にストレスを管理していきましょう。