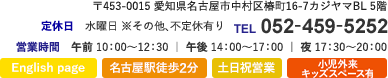2025/04/22
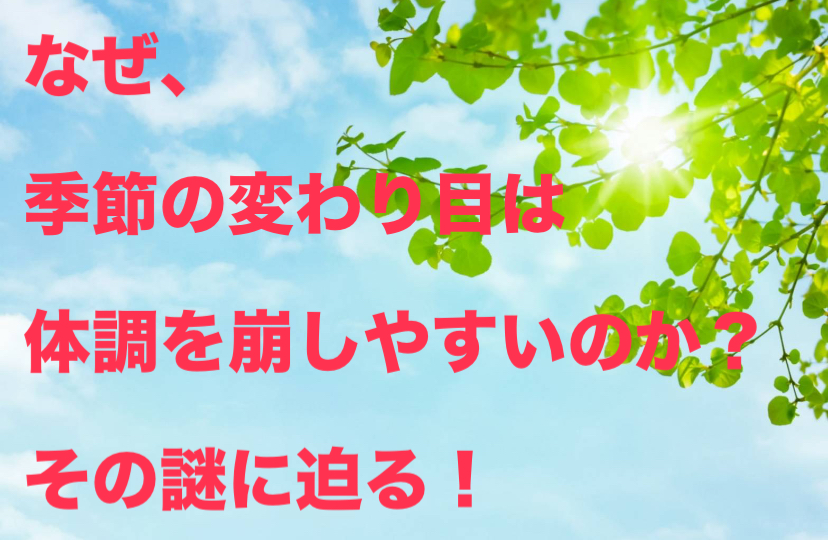
こんにちは!
あれだけ寒かった日はもうどこに行ったのか、昼間は最早暖かいを通り越して暑いくらいですね。こんなふうに、冬から春、春から夏、夏から秋、秋から冬へと移り変わる季節の中、私たちは気温や気候にうまく身体を合わせて生活しています。ただ、うまく合わせると言ってもいつもすんなりといくわけではありません。特に、季節の変わり目は、多くの人が体調を崩しやすい時期ですね。今回は身体的、環境的、そして精神的な面から、季節の変わり目に体調を崩しやすくなる要因について、そして元気に過ごすための対策方法について書いていきます!
まずは身体的な要因から書いていきます。

◯身体的な要因
1.身体の生理的反応
季節が変わることで特に変化を感じるものといえば、皆さまはなにが思いつくでしょうか?色々な意見があると思いますが、ここでは一旦「気温」を特に変化を感じるものとして書いていきますね。
さて、気温の変化は私たちの身体にどのような影響を及ぼすのでしょうか?たとえば、冬から春にかけての温度の上昇に対して、身体はその変化に適応しようとします。この過程で、自律神経やホルモンバランスが影響を受けることがあるのです。自律神経は交感神経と副交感神経から成り立っています。例えば気温が下がった時、自律神経の交感神経が働いて体温を維持するために熱を作り出します。また、気温が上がった時は血液量を調整したり、汗をかくという身体活動を促したりと、体温を一定に保つための働きをしてくれています。
では、これがかなり多くの頻度と回数で行われたら?
そして寒暖差が大きかったら?
ご想像のとおり、適応していく毎に疲労が蓄積し、自律神経がうまく働かなくなってきます。
更に日照時間の変化についても考えていきましょう。冬から春に季節が変わると日光を浴びる機会が増えます。人間は朝起きて太陽の光を浴びると目から脳に信号が伝わり、脳内で働く神経伝達物質の一つであるセロトニンという物質が作られます。そうすることで睡眠に関わるホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、体内時計が調整されます。冬と春ではもちろん日照時間が違います。冬から春に季節が移り変わった直後はまだ冬の生活リズムに慣れているため、私たちの身体の中は私たちが意識していないところで適応するために目まぐるしく働いているのです。
そして気温や日照時間の変化に加えて、春は花粉症などのアレルギー反応が増える時期でもありますね。これ以外にも黄砂や乾燥、紫外線、気圧の変化など、冬から春に変わるだけでも私たちの身体にとって気をつけなければならないことが多くあります。こうした様々な外的要因に対して身体は生理的に反応し、一定の状態を保とうとしてくれているのです。
2. 自律神経の機能低下と免疫機能の低下
身体が季節の変わり目に起こる色々なことに対応してくれている中で、注目したいのが免疫機能についてです。繰り返しになりますが、自律神経は交感神経と副交感神経から成り立っています。自律神経は呼吸や体温、血圧、消化など私たちの生命維持に欠かせない機能を調節する神経です。例えば、少し前にお話した通り、気温の変化に合わせて自律神経が働いて私たちの体温は調節されています。寒いところに居すぎればもちろんその体温を維持するのが難しくなってきます。暑すぎても同じことが言えます。そう考えると、朝と夜肌寒く、昼暑い状態という一日の中で忙しなく気温が変わる季節の変わり目の中、自律神経がたくさん働いてくれていることは想像しやすいですね。
そうやってたくさん働いた自律神経の機能が低下してきた時、気をつけたいのが免疫機能の低下です。自律神経は交感神経と副交感神経が交互に優位になることで免疫機能も支えてくれているのです。交感神経が優位な時は、顆粒球の比率が上がります。顆粒球とは、殺菌作用がある成分をもつ白血球の一種です。そして、副交感神経が優位な時はリンパ球の比率が上がります。リンパ球とは、抗体を作って抗原を攻撃したりする白血球の一種です。自律神経が正常に機能しているときは、交感神経と副交感神経が、バランスよく体内の環境を維持できます。
しかし、例えばバランスが崩れて交感神経がずっと優位な状態が続くと、顆粒球が増えます。顆粒球が増えすぎると、顆粒球が殺菌に使う活性酸素や酵素が健康な細胞を破壊する恐れがあります。そして、顆粒球が発生させる物質にはリンパ球の働きを抑える性質があるため、顆粒球が増えすぎるとリンパ球が減って、ウイルスに対する抵抗力が低下するのです。自律神経のバランスを保つことで、私たちの体内にある様々な役割をもつ白血球も、上手く働くことができるのです。
以上、季節の変わり目に体調を崩しやすくなる要因として、身体の生理的反応、自律神経の低下と免疫機能の低下について書いてきました。こうしてみると普段何気なく生活しているようで、実は身体の中では色々なことが起こっていますね。
それでは次に、環境的な面から見た要因について書いていきます。

◯環境・生活習慣の変化
先ほどは項目で季節が変わることで特に変化を感じるものの一つとして、気温と日照時間を挙げました。その変化に私たちの身体が対応していくように、私たちの行動自体も合わせて変わっていきます。例えば冬の寒い日ですと、あたたかい屋内から屋外に出ることが億劫になり、必要最低限の外出で済ませることが多くなったり、冷えで身体の動作が緩慢になり、つい運動不足になってしまうこともあるのではないでしょうか。そして、冬から春になると気温も上がって過ごしやすい日が増え、日照時間も長くなって活動的になり、行事ごとも増え行楽に出掛ける機会が増える方も多いのではないでしょうか。
このように、季節に合わせて私たちの体内だけではなく、行動自体も変わっていくのです。ただ、急激にアクティブになりすぎることで身体に負担をかけることがあります。冬から春に変わり、気温が上がって運動しやすいからといって、急に長距離のランニングを始めたり、過激な筋トレを始めてしまうと怪我にも繋がります。また、出掛ける機会自体が増え、知らず知らずの間に疲労が溜まって体調不良を崩す可能性もあります。あまり無理はしないように過ごしていきたいですね。
次に、精神的な要因について書いていきます。

◯精神的な要因化
季節の変わり目といえば、色々な事に区切りになることが多いのも注目したいポイントです。特に春は入学式や入社式など、新しいスタートや出会いの季節です。楽しみでもある一方で、そういった変化によるストレスを感じやすい時期でもあります。新しい環境や人間関係に適応する過程で、緊張や不安を抱えることが多く、身体に影響を及ぼすことがあります。緊張や不安などの感情を抱えた状態が続くと、今度は動悸や震え、息苦しさ、冷や汗といった変化が身体に現れ始めます。そして暴飲暴食、生活リズムの乱れ、そわそわと落ち着きがなくなるなどの行動に繋がっていきます。
とはいえ、ストレスを完全になくしてしまうと今度は逆に張り合いがなく、人生がつまらないと感じるようになってしまったりします。大切なのはストレスと上手く付き合っていくことです。そのためにも、ストレスが溜まる前に解消していくことがポイントになります。
次は季節の変わり目に負けないよう、体調を崩さないための対策方法を書いていきます!

◯体調を崩さないための対策方法
1.質の高い睡眠の確保
規則正しい睡眠を心がけ、質の高い睡眠を得ることが大切です。寝る前に38〜40度のお湯にゆっくり浸かることで、睡眠の質を向上させることができます。入浴中はたくさん汗をかくので、入浴前と入浴後のそれぞれでコップ1杯の水を飲むのもおすすめです。
2.栄養バランスの良い食事
栄養が偏ると身体の不調を招きやすくなります。生活習慣病のリスクや、免疫機能の低下などを防ぐためにも、バランスの取れた食事を取ることが大切です。日常の食事の中で不足しがちな栄養素として、たんぱく質、ビタミン、ミネラルを意識して摂取しましょう。スマートフォン向けの食事管理アプリをインストールして、日々食べている物の栄養を管理することで、どのような栄養が不足しているのかを確認するのも良いでしょう。
3.適度な運動
ウォーキングや軽いストレッチなど、無理のない範囲で活動することがおすすめです。特に毎日30分程度のウォーキングは、特別な準備が不要、血行促進、筋力アップ等のメリットがあります。もしまとまった時間を取ることが難しい場合は、10分のウォーキングを1日3回行っても大丈夫です。
4.ストレス管理
音楽を聴いたり、読書をするなど趣味やリラックスできる時間を作ることで、ストレスを軽減することができます。また、深呼吸や瞑想などを隙間の時間に取り入れるのも良いでしょう。ストレスを感じた時、知らず知らずの間に呼吸が浅くなっているケースがあります。呼吸が浅くなることで交感神経が優位になり、心身をより緊張させてしまう可能性があるのです。ストレスを感じた時に深呼吸をするのも、ストレス管理の手段の一つになります。先ほどお話したように、大切なのはストレスと上手く付き合っていくことです。そのためにも、ストレスが溜まる前に解消していけるよう日頃から意識していきましょう。

いかがだったでしょうか?
私たちの身体は、季節の変わり目の中で起こる様々な変化を日々受け止めて、私たちが意識していないところで色々な働きをしてくれていますね。これらの働きを円滑にしておくためにも、日頃から対策することでいつまでも健康に過ごせるようにしていきましょう。
最後に、体調管理とカイロプラクティックについて書いていきますね!
◯体調管理の一助としてのカイロプラクティック
こちらの項目では、前項に加えてカイロプラクティックを体調管理の一助とするメリットをお伝えしていきます。
カイロプラクティックは、体調管理や健康促進において重要な役割を果たす代替医療の一つです。身体の構造(特に脊椎)と機能に注目し、神経の円滑な流れを妨害してしまっている可能性のある骨格を正確に分析し、手技によって調整することで身体の自己治癒力を高めることを目的としています。また、カイロプラクティックの施術を受けることは予防にも繋がります。身体の問題が症状として顕在化する前に定期的に施術を受けることで、健康を維持し生活の質を向上させる手助けとなります。総じてカイロプラクティックは体調管理の一助として非常に効果的な手段であり、健康な生活を送るための重要な要素となるでしょう。健康を維持するために、カイロプラクティックを取り入れてみることをお勧めします。
庵原崇カイロプラクティックオフィスでは、毎月限定で先着3名の方に無料個別相談会を受け付けております。施術を受けられるかどうか迷っておられる皆さまに、ぜひご利用いただきたいと思います。