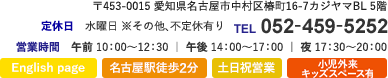2025/03/28


こんにちは!
今回はスポーツ中に、何度も同じ箇所を痛めてしまってスポーツを楽しめないという方に向けた記事となっています!
「ちゃんとケアしているはずなのに、また痛めてしまった…」「マッサージやストレッチをしているのに、なぜ何度も同じところが痛くなってしまうのか…」といった、スポーツ中のケガに悩まされていませんか?
ケガをしないように気をつけているのに、なぜまた起きてしまうのか?もしかすると根本的な原因に対してのアプローチができていないのかもしれません。
この記事では、マッサージ・ストレッチ・テーピングなどの一般的なケアと異なる視点から、カイロプラクティックによる根本的な改善方法をご紹介していきます。
さらに、何度もケガをしないためには予防が大切です。自宅でも取り組める簡単な予防方法についても分かりやすくお伝えしています。
何度もケガを繰り返したくない!と思っている方には、ぜひ読んで頂きたい内容となっていますので、最後まで読んでみてください!
1. ケガの種類
ケガはきっかけによって2種類に分けられ、スポーツ外傷とスポーツ障害によるものに分けられます。
スポーツ外傷とは突発的に発生するものです。スポーツ障害とは、繰り返される同じ動作による負荷により発生します。
スポーツ外傷とスポーツ障害への対処法が異なりますので、いくつかご紹介します。
- ① スポーツ外傷の特徴
- スポーツ外傷は転倒、衝突、急激な回旋力や伸張力などによる1回の急激な力により、突発的に発生するケガです。患部には腫脹、発熱、発赤が見られます。
主に骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れ、神経損傷、腱損傷または腱断裂、血管損傷によるものがあります。 - ② スポーツ障害の特徴
- スポーツ障害は、長期間に繰り返される過度の運動負荷により生じる筋肉、骨、腱、靭帯などの慢性炎症を言います。
種類 原因 特徴 スポーツ外傷 突発的に発生 患部の痛み、腫脹、発熱、発赤、熱感 スポーツ障害 繰り返される動作により発生 運動痛 - スポーツ障害の例
- 筋肉:筋筋膜性腰痛
腱 :アキレス腱炎または断裂・膝蓋腱炎・野球肩・テニス肘・ゴルフ肘
靭帯:腸脛靭帯炎
神経:手根管症候群・胸郭出口症候群
軟骨:オスグッドシュラッター病・シーバー病

2. ケガに対するアプローチ
スポーツ外傷とスポーツ障害のアプローチ方法も異なります。ケアの方法を誤ると症状を助長させてしまう恐れがありますので、ケガをしてから回復するまでの過程やアプローチ方法を見ていきましょう。
- ① スポーツ外傷が発生してから回復するまでの過程
- スポーツ外傷を発症してから回復するまでに様々な過程をたどり、患部が回復します。 回復までの過程の目安をみてみましょう。
特徴 日数 急性期 痛みが強い 発症〜2週間 亜急性 痛みは軽減するが上手く動かせない 発症〜6ヶ月 慢性期 痛みは軽い 1年〜2年 - ② 急性期に対してのアプローチ方法
- 急性期の特徴は患部に炎症物質が集まるため、患部の痛み、腫脹、発熱、発赤、熱感が見られることが特徴です。そのため患部を温めてしまうと炎症症状を助長させてしまう恐れがあります。
早期に回復させるためには何が必要かを見ていきましょう。 - 安静:運動を中止することで、全身の血液循環を抑えて患部への血流量を減らします。
患部の固定により損傷部位の動揺を防ぐことで局所的な安静をはかり、体内の循環が活発にならないよう全身的な安静も必要なため、座るなどして動かないようにします。 - 冷却:患部の冷却により、疼痛を緩和させることが可能です。
炎症によって過剰に高まった局所の熱感を下げることで血管を収縮させ、患部の血流を減少させて内出血を抑えます。 - 圧迫:損傷した細胞や毛細血管から、細胞液や血液の漏れを防ぎます。
また大量に血液が流れ込むのを抑制するとともに、血液が残存することを防ぐことが可能です。
弾性包帯やバンテージを用いて適度な圧迫が加わるように巻くと良いです。 - 挙上:重力などの影響で内出血が進むのを防ぐために、患部を心臓よりも高い位置にします。例えば両脚の場合は横になり、イスやクッション、座布団などで足を高く持ち上げることが有効です。
- ③ スポーツ障害が発生する原因
- スポーツ障害は、主に疲労の蓄積が原因で発生することが多いです。疲労が回復していない状態で運動を再開した時や、誤った体の使い方を繰り返すとスポーツ障害に繋がります。
- ④ スポーツ障害に対してのアプローチ方法
- スポーツ障害には様々なアプローチ方法が見られますが、主に使われている代表的なアプローチ法を見ていきましょう。
- マッサージ:マッサージは筋肉に直接触れて、揉む、さする、抑えるなど筋肉の緊張や血行不良が原因の慢性痛に有効です。
- テーピング:元々はスポーツ選手が負傷を予防、もしくは負傷した部位の悪化を防止するために、関節、筋肉などにテープを巻いて固定することを目的とされていましたが、現在ではケガの応急処置や、予防・再発防止、パフォーマンスアップを目的とされていることが多いです。
- ストレッチ:ストレッチは、柔軟性を高めるための運動として開発されました。 身体をリラックスさせたり疲れをとったり、体調を整えることに有効です。

3. スポーツケアには、カイロプラクティックがオススメ!
ケガを繰り返してしまうときに、どのようなケア方法を選んでいますか?
「ちゃんとケアしているはずなのに、また痛めてしまった…」「マッサージやストレッチをしているのに、なぜ何度も同じところが痛くなってしまうのか…」この様に悩んでいませんか?そこでオススメしたいのがカイロプラクティックです!
マッサージ・テーピング・ストレッチなどとは異なり、カイロプラクティックは根本的な原因にアプローチし、ケガの早期回復や予防に高い効果を発揮します。
カイロプラクティックとは何か、そのアプローチ方法や期待できる効果を初めての方でも分かりやすく解説していきます。
- ① カイロプラクティックとは?
- カイロプラクティックは約130年前にアメリカで誕生しました。創始者のD・Dパーマーが、自宅の掃除夫の首を調整したところ、彼の数年来の難聴が改善されたことが始まりでした。後に、D・Dパーマーの患者で友人でもあったサムエル・ウィードによって、ギリシャ語で「手」を意味するカイロと、「技術」を意味するプラティコスを組み合わせてカイロプラクティックと命名されました。その名の通り、手技による身体の、特に背骨を調整することで、神経系の働きを正常化し、自己治癒力を高める事を目的とした療法です。
身体が本来持つ自己治癒力を引き出すことで、ケガからの早期改善のみならず、ケガの予防にも有効です。 - ② カイロプラクティックのアプローチ方法
- カイロプラクティックの名前を聞いたことがある方の中には、背骨をボキボキする治療法と思われている方もいらっしゃるかもしれません。本来であればカイロプラクティックの目的は、アジャストメントという手法を用いて神経に影響を与えている背骨のみを瞬間的に動かし関節の機能を整えます。アジャストメントにより、神経機能が回復することで身体の自然治癒力が高まり、ケガからの早期改善や予防に効果的です。
- ③ カイロプラクティックで期待できる効果
- カイロプラクティックでは、スポーツや運動に様々な効果を発揮します。以下に効果をまとめてみました。
効果 詳細 疲労回復の向上 神経機能が高まることで、身体を修復させるために自己治癒力が向上する。 パフォーマンスの向上 神経機能が高まることで脳と神経のネットワークが上手くいき、自身のパフォーマンスが向上 関節の可動域が向上 特に睡眠の質が上がり、身体の回復力が向上する。 自然治癒力の向上 特に睡眠の質が上がり、身体の回復力が向上する。 筋肉の柔軟性が向上 身体の回復力が向上することで、筋肉の緊張も早期に回復しやすい。 - ④ 一般的なスポーツケアとカイロプラクティックの違い
- ここではスポーツ障害を取り上げ、一般的なケアと、カイロプラクティックのアプローチ法の違いを見ていきましょう。手法や目的が違うのでそれぞれの特性がありますので、理解した上でご自身に合ったケアをお勧めします。一般的なケアは主に筋肉・靭帯・腱などといった直接的なアプローチを行い血行促進や筋肉の緩和を目的とします。カイロプラクティックは骨格の問題、特に背骨の調整に重点を置いています。
項目 一般的なケア カイロプラクティック 施術箇所 筋肉・靭帯・腱 神経に問題を起こしている背骨 目的 血行促進・筋肉の緩和・疲労回復 神経機能の正常化 手法 マッサージ・テーピング・ストレッチ アジャストメント

4. ケガをしないためのセルフケア
ケガを早期改善、予防に導くためには様々な治療法の選択が大切です。それに加えて自宅でのセルフケアも同時に行うことが大切になってきます。下記では自宅で簡単に取り組めるセルフケアの解説をしていきます。
- ① 入浴
- 温熱作用:お湯に浸かり身体を温めることで、血管が拡張し血液やリンパの流れが良くなり、代謝が活発になります。その結果、筋肉の柔軟性の向上が期待できます。
- 静水圧作用:水圧によるマッサージ効果が期待でき、下半身に溜まりがちな血液や疲労物質を心臓へ送り返すことが期待できます。
- 浮力作用:入浴時は、重力による負荷が軽減されるので、負荷が加わり続けているところを軽減させ、症状を軽減することが可能です。また筋肉の緊張が軽減されるので、リラックス効果が加わり睡眠の効果を向上させることが期待できます。
- ② 睡眠
- 身体は睡眠をとっている時に回復します。特に睡眠中は成長ホルモンが分泌されますので、疲労の回復や
傷ついた身体の修復に取り掛かります。そのため筋肉の発達にも必要になってきます。質の良い睡眠が取れていると、ケガからの早期改善や予防が可能です。 - ③ ストレッチ
- ストレッチには身体を動かしながら行う動的ストレッチと、筋肉をジワーッと伸ばすように行う静的ストレッチがあります。
- 動的ストレッチ:動的ストレッチは身体を動かしながら行うので、ウォーミングアップにも有効です。
特にラジオ体操は様々な筋肉を使いストレッチを行うので、運動前はとても効果的です。 - 静的ストレッチ:筋肉をゆっくり伸ばす方法です。クールダウンとしてよく使われるストレッチ方法なので、睡眠前や運動後に行うと効果的です。
5. まとめ
スポーツ外傷やスポーツ障害のアプローチ方法は様々です。
その改善策としてマッサージ、テーピング、ストレッチ、カイロプラクティックがありますが、効果も様々です。マッサージ、テーピング、ストレッチケアは主に患部に対して有効です。一方でケガを何度も繰り返してしまう場合は、神経機能が低下しパフォーマンスが落ちてしまっている状態の可能性もありますので、カイロプラクティックによる調整が有効となります。
どの方法もケガの早期改善や予防に有効です。ご自身の状態に合った方法を選択することがとても大切になってきます。医療機関でのケアも大切ですが、日常生活でもセルフケアを取り入れることも大切になってきます。スポーツで何度もケガを繰り返してしまう、なかなか思うように身体が回復しない方は、まず自分の状態を把握することから始めることをお勧めします。そして自分自身に合った、お身体のケア方法を選んでいきましょう。何かお困りごとがありましたら、当院へお問い合わせください。